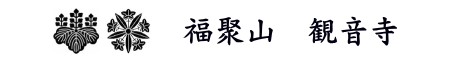曹洞宗の流れは、インドでお生まれになられたお釈迦さまの教え・おさとしを、幾世代にも渡って祖師方が悟りの生活を通して師匠から弟子へと受け継ぎ、インドから中国そして日本に伝えられてきたものです。 曹洞宗の源はお釈迦さまですから、ご本尊さまはお釈迦さまです。そして、お釈迦さまの教えを日本に伝えられ、道元禅師を「高祖」とあがめ、瑩山禅師を「太祖」と仰ぎ、このお二人の祖師を「両祖」と呼び、この三師を「一仏両祖」としてお祀りしお慕い申し上げ、信仰の誠を捧げているのです。 拝む時は「南無釈迦牟尼仏」と、お唱えして礼拝します。
永平寺
福井県吉田郡永平寺町にある曹洞宗の寺院。總持寺と並ぶ日本曹洞宗の大本山であります。山号を吉祥山と称し、寺紋は久我竜胆紋であります。開山は道元禅師、本尊は釈迦如来・弥勒仏・阿弥陀如来の三世仏であります。 大本山永平寺は1244年、道元禅師が45歳のとき、波多野義重公の願いによって、越前(福井県)に大仏寺を建立し、2年後に吉祥山永平寺と改められたことに始まる(坐禅)修行道場であります。 寺号の由来は中国に初めて仏法が伝来した後漢明帝の時の元号「永平」からであり、永久の和平という意味であります。 道元禅師示寂後の永平寺は、2世孤雲懐奘、3世徹通義介のもとで修行と整備が進められた。しかし4世義演の時、外護者波多野氏の援助も弱まり、一時は廃寺同然まで衰微したが、5世義雲が再興し現在にいたる基礎を固めました。 1372年、後円融天皇より「日本曹洞第一道場」の勅額を受け、1615年、徳川幕府より法度が出され總持寺とともに大本山となりました。 深山幽谷の地にたたずむ山門、仏殿、法堂、僧堂、庫院、浴室、東司の七堂伽藍(伽藍:僧侶が修行する清浄な場所)では、今も修行僧が道元禅師により定められた厳しい作法に従って禅の修行を勤めています。
≪總持寺≫
能登に諸嶽観音堂という霊験あらたかな観音大士を祀った御堂がありました。そこの住職である定賢権律師が、元亨元年(1321)4月の晩のこと、夢枕に僧形の観音様が現れ、「永光寺に瑩山という徳の高い僧がおる。すぐ呼んでこの寺を譲るべし。」と告げて、姿を消されたというのです。その5日後の明け方、羽咋の永光寺方丈の間で坐禅をしていた瑩山禅師も同じような夢のお告げを聞きました。禅師と律師はともに感応道交し、律師は一山を寄進し、禅師は快く拝受しました。 寺号はここに仏法が満ち保たれているとして「總持寺」と改名し、山号は諸嶽観音堂の仏縁にちなんで「諸嶽山」とし、翌元亨2年(1322)瑩山禅師59歳の時、後醍醐天皇により、「曹洞出世の道場」に補任され、總持寺は曹洞宗の大本山たることとなりました。 瑩山禅師によって開創された大本山總持寺は、13000余ヶ寺の法縁寺院を擁し、能登に於いて570余年の歩みを進めてまいりましたが、明治31年(1898)4月、本堂の一部より出火、伽藍の多くを焼失してしまいました。明治38年(1905)5月、本山貫首となられた石川素童禅師は消失した伽藍の復興のみでなく、本山存立の意義と宗門の現代的使命の自覚にもとづいての大決断をもって、明治44年(1911)11月に寺基を鶴見の地に移され、同時に能登祖廟を大本山総持寺祖院とし、今に至ります。